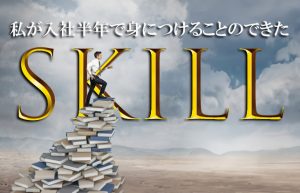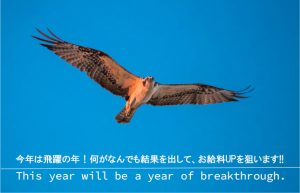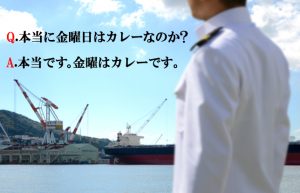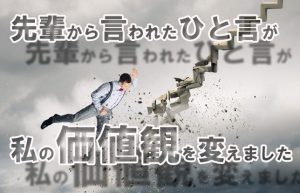こんにちは、錦糸町エリア担当のまっつーです。今回もお金に関するお話がテーマになります。
平均貯蓄額とお金の保管場所
サラリーマンや公務員でも、自営業でも、普通預金口座が財産管理のベースになっています。給与や売上が入金され、そこから生活費や様々な支払いを行います。

自営業の場合は当座預金を利用することがありますが、個人の口座は普通預金でお金の管理をしているでしょう。
決済用口座である普通預金口座にお金を入れっぱなしでは、お金を貯めることはできません。単に金利が0.001%と最低水準であることだけではなく、お金を貯める正しい場所ではないからです。
総務省によると、二人以上の勤労者世帯の平均貯蓄額は1299万円で、その預け先として銀行の普通預金の額は339万円で約26.0%を占めます。
年収区分で一番低い層(平均345万円)の世帯の平均貯蓄額は692万円で、このうち銀行の普通預金の額は194万円で28.0%を占めます。
年収区分で貯蓄額は異なりますが、預け先としてはおおよそ平均と同じような割合です。
このデータを見たとき、約200万円(全体平均で約339万円)ものお金が普通預金口座に入れっぱなしであることに驚かされました。
本当にこれだけのお金を普通預金口座にプールしておく必要があるのでしょうか?
1カ月の収支がそれほど変動しないのであれば、万一に備えて2、3カ月分の生活費を普通預金口座に残しておけばいいのではないでしょうか。
お金の役割を見直してみる
どこにあろうとお金はお金。価値あるものに変わりはありません。しかし、お金には大きく3つの役割があります。「使う」「貯める」「増やす」です。

最終的には、どこかのタイミングで「使う」ことにはなりますが、
- 日常的に「使う」お金
- 5年~10年以内に使うお金を「貯める」
- 使う時期は未定、または老後資金として使うので、少しでも「増やす」
という3つの役割に分けることができます。
このすべてを普通預金だけで済まそうとするには無理があり、無駄でもあります。
混沌とした世界情勢、先行きの見えない日本の将来を見据えた時、もはや普通預金だけで、面倒くさがっているわけにはいかないのです。
また、結婚して家族が増え、様々なライフイベントにかかるお金を確実に貯めようとしたときに、普通預金しか利用していない場合、生活費、旅行費用や冠婚葬祭などの特別支出用のお金も一緒に管理することになります。
さらに、住宅購入の頭金、子どもの教育費まで同じでは、何の目的のお金をどれだけ貯められたかを把握することは不可能です。
老後資金に関しても、「最後に残ったお金が老後資金」という感覚では、漠然とした不安を抱えたまま何十年も過ごすことになってしまいます。
お金には3つの役割があることを改めて理解し、正しい場所に置き直す必要があるのです。